Magic: The Gathering
Oriental Gold
This Novel is written by Shurey
Prologue / Sec.1
 |
第一章 |  |
|---|---|---|
| 胎動 | ||
第二話 紅 沙蘭
Fireball | [Sorcery] |
| Pay | |
 |
第一章 |  |
|---|---|---|
| 胎動 | ||
Fireball | [Sorcery] |
| Pay | |
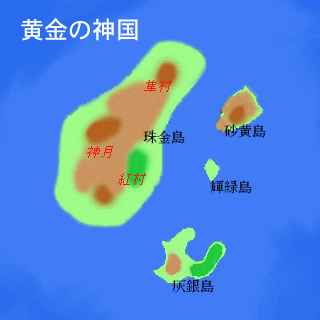 大陸の東の海上に浮く島国は「黄金の神国」と呼ばれている。最も大きな珠金島(しゅきんとう)、その横に砂黄島(さおうとう)、輝緑島(きりょくとう)、灰銀島(はいぎんとう)が縦に並んでいた。珠金島以外は余り人の住まない場所だった。その珠金島の中心に、龍が天に昇るがごとくそびえ立つ昇竜山があった。岩肌のゴツゴツとした峰が頂まで極端に垂直で、その姿が龍のごとくたくましく、人をよせつけない厳然たる偉容であった。
大陸の東の海上に浮く島国は「黄金の神国」と呼ばれている。最も大きな珠金島(しゅきんとう)、その横に砂黄島(さおうとう)、輝緑島(きりょくとう)、灰銀島(はいぎんとう)が縦に並んでいた。珠金島以外は余り人の住まない場所だった。その珠金島の中心に、龍が天に昇るがごとくそびえ立つ昇竜山があった。岩肌のゴツゴツとした峰が頂まで極端に垂直で、その姿が龍のごとくたくましく、人をよせつけない厳然たる偉容であった。
その昇竜山のふもとに神国の中心都市、「神月(しんげつ)」があった。首都とはいえ王族とそれに仕える者と自由市場に集まる商人達が住んでいるだけだった。大きなマーケットは近くの町や村から行商人が毎日やって来て成り立っている。
その地を統べる神王は3つの王家の代表が5年毎に交代で務めていた。軍事を司る雷(いかづち)王家、政治を司る源(みなもと)王家、祭事を司る鳳(おおとり)王家の三王家が頂天に君臨し、それぞれの傍系の家が王家に従って国家の大事を司っていた。
諸家の子供達は16才から18才まではそれぞれの魔法学校で魔法の基礎を学び、次の2年間を首都神月で王家に仕えて生活する。特に、魔法に素養のある選ばれた者は神月の魔導学院で同じ2年間に応用魔法を学ぶことになる。
このように黄金の神国では魔法を学ぶのは一部の者だけではない。王家やその諸家には魔法の素養に溢れ、生活の中でも魔法と精霊との関わりが深く、長き年月に積み重ねられた英知によって支えられていた。
魔法を使う者は幾つかの階級に分けられていて、基礎魔法を学んだ者を魔術師(Magician)、応用魔法を使う者を魔法師(Sorcerer)と呼び、主に医療の為にその術を使用する。次に高等魔法を学び、魔導師(Wizard)となる。そして、最高の称号が魔導主師(Master Wizard)であった。
現在、この4つの島からなる神国を雷王家の紫光(しこう)神王が国家を統べていた。彼もまた最高の魔導主師の一人であり、人は「魔導師の鑑」と賞賛していた。
| 紗蘭 | 涼 | 朧 |
| 翔 | 重継 | 春菜 |
| 茜 | 紫苑 | 霞 |
| 疾風 | 夜叉 | 腕 |
| 若葉 | 龍 | 澄 |
| 飛燕 | 冷輝 | 紫苑 |