Magic: The Gathering
Oriental Gold
This Novel is written by Shurey
Prologue / Sec.1 




 |
第一章 |
 |
| 胎動 |
|---|
第四話 王 麗
Lhurgoyf | [Creature]
*/1+*    |
| Lhurgoyf has power equal to the number of creature cards in all graveyards and toughness equal to 1 plus the number of creature cards in all graveyards.
|
王家末裔
ノイバンシュタイン城は切り立った岸壁の遙か上、霧の向こうにその影をのぞかせていた。海からは常に霧が立ちこめ、沖には暗礁が多く、漁師の舟さえ近付くことはなかった。
岬の先端にそびえる城へは広大な森を通り抜けなくてはならない。だが、森の自然が、様々な野獣たちが人々の接近を阻んでいるのだった。
城には幾つかの塔が立ち並んでおり、中心には最も高い尖塔が建っていた。その上空に大きな翼が舞っていた。それは二つの固まりを足下にぶら下げながら、ゆっくりと城の上空を旋回し、静かに一つの塔の上に降りて行く。
足下の二つの影が動き、塔の頂上へ降り立った。ケープをまとった女と虎の頭を持った男であった。そして、上空にいた大鷲の羽を持つ男が翼を収めて降りてくる。
鉄の扉を開けて、女を先頭にした3人が暗い塔の内部へと狭い石段を降りて行く。
「ラムザ様、お帰りなさいませ」
背中の曲がった老翁アスターが彼らを出迎えた。彼はこの城に古くから使え、ラムザたちの世話をしているのだった。
「ああ、遅くなった・・」
疲れた声を漏らしたラムザはケープを脱ぎ捨て、小さな簡易ベッドに全身を預けて仰向けに倒れ込む。その姿は実に繊細で美しいガラス細工のような高貴な輝きを発していた。ただ、体の右半身を覆う赤黒いアザが痛々しく目に焼き付く。
全身が筋肉と鋼の体毛に覆われた虎男のラゴルですら、ため息を吐いて椅子に寄りかかった。
だが、一番疲れているのは二人を運んできた天使のような姿のロムルである。足や翼を力無く振るわせて立っていたが、静かに前のめってベッドへ倒れてしまうのだった。
「では、私はアベル様に報告に参ります。ミレ、後は頼んだぞ」
「はい、お父様」
老人は娘を残して、その部屋を出ていった。ミレは小柄な中年女性で、細い頬に細く長い目をしていた。しかし、時々見せる小さな瞳はどこか冷めていて、まるで彼らの行く末を知っているようであった。
「さあ、浴室の準備ができいます。下へ」
ぶっきらぼうなミレの言葉に誰も応えなかった。というより、彼女の声が聞こえないくらい疲れていたのだ。
「聞こえないの?お風呂を用意したのよ・・・」
「・・聞こえたよ。おい、ラムザ。先に行って来い、俺は最後でいい。ロムルもしばらく動けそうにない」
妙に優しい口振りのラゴルであった。その声に反応してか、ラムザがゆっくりと体を起こした。
ミレはフラフラと立ち上がるラムザに思わず手を差し伸べて、苦々しく口元で笑っていた。そのまま彼女の体を引きずるように部屋の外へと連れ出して行った。
その頃、老人アスターは3人のいる塔の隣にそびえる赤い屋根の尖塔に向かっていた。
その広間の正面には黄金で作られた玉座とおぼしき椅子が一脚。そこに一人の紳士が座っていた。
彼の両脇後方には鉄の甲冑で身をくるんだ偉丈夫が立ち、紳士の前には5人の若く美しい女性たちが食事の準備をしている所であった。
とても豪華な食事には見えないのは彼が菜食主義者であるからだ。それでも工夫を凝らした数多くの料理が並べられている。
そんな所にアスターが静かに現れた。
「アベル様。お食事でしたか・・・」
彼は紳士の前に立つと、深々と頭を下げた。
「いや、これからだ。ラムザたちが戻ってきたのだな」
それは優しく鋭意な声であった。彼はこの城の若き主、アベル・ノイバンシュタイン伯爵であった。その髪は黄金で編んだように輝いていた。その奥にある瞳は緑がかった不思議な青色をしていて見る者を吸い込むようであった。もうすぐ37才になるが、小さく張りのある細い顔に、女性のように引き締まった体は彼のうちに秘めた力の象徴であった。
その口元にくわえたタバコからゆっくりと白い煙が上がっている。
「さすがですな。しかし、3人ともかなり疲れている様子で、立つこともままならぬようでした」
「そうだろう、初めてこの城を出たのだからな。彼らにも温かい食事を用意してやってくれ」
アベルは淡々とした口調で、どこか几帳面というのか、神経質な印象を与える。
「分かりました。それでは、ごゆっくり・・」
アスターは静かに退室していった。
それを見送ってからアベルはタバコを消すと、水を一口含んだ。ゆっくりとフォークを手に取り、生のレタスに突き刺した。
「ああ、生き返る・・」
虎男のラゴルは両手で丸焼きになった鶏肉を持ち上げて、ガツガツと食べていた。
ロムルは黙々とブタの肉を細かく切って口に運んでいた。
ミレの指示で次々と料理が運ばれて来ては、空の皿が戻って行く。その度に、彼らは徐々に生気を取り戻して行くのだった。
そんな彼らを後目に、レタスを手でちぎって口に運ぶラムザ。
「ラムザ様、あまり食が進まぬようですが・・・」
彼らの様子を脇で見ていたアスターがそっと声をかけた。ラムザはそれにも答える風でなく、ひたすら野菜だけを食べている。
「まあ、よろしいでしょう。ですが、余りお体もよろしくないのですから、しっかり体力のつくものを口にしておいた方がいいですぞ」
「ラムザ。アスターの言うとおりだ」
ロムルも心配そうに彼女を見ていた。ラゴルも一瞬手を休めて、横目でその様子をうかがいながら再び鶏肉をほおばった。
「・・分かったわよ。大丈夫。ちょっと、色々あったものだから・・・」
みんなの眼差しに苦笑混じりの笑顔で答えながら、フッと肩の力を抜いたようだ。
「仕方ありません。幼い頃に失った故郷への旅だったのですから・・・」
「・・フフッ。そんなんじゃないわ」
それは自嘲的な笑いであった。しかし、それもまた妖しげな艶やかさを秘めて響くようだ。
「でも、そういうことなのかしら・・・」
ちょっとためらうように、ラムザはエルフの村で出会った翔たちのことを思い出していた。
自分たちが灰にした故郷を見たときさえ何も感じなかったのだ。しかし、自分のことを何の疑いもなく信用して受け入れてくれた彼らのことは不思議で仕方がなかった。どうしてああいうことができるのか、幾ら考えても彼女には分からないことだった。
どちらにしても、自分が人の心を探ろうと思いを巡らすことだけでも新鮮なことであった。
「まあいいわ。ラゴル、私の分まで食べないで」
そう言うと、ラゴルから食べかけの鶏肉を取り上げてかぶりついた。
呆気にとられた男たちも、次の瞬間には目を潜めて笑っているのだった。
ラムザ、ラゴル、ロムル。それは彼らの本当の名前ではなかった。彼らはその名前を受け入れることで過去を捨てる決意をしたのだ。
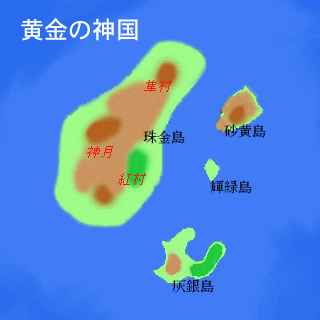 黄金の神国は珠金島と3つの島を領土としている。砂黄島には砂丘があり、輝緑島には深い森がある。そして、南にある灰銀島には人を寄せ付けぬ海流があった。
黄金の神国は珠金島と3つの島を領土としている。砂黄島には砂丘があり、輝緑島には深い森がある。そして、南にある灰銀島には人を寄せ付けぬ海流があった。
その灰銀島に一団の移住者がやってきたのは西暦2220年のこと。大陸に生まれた王戒(おう・かい)という男とそれに付き従う数名の男女であった。
王戒は身分を隠して神国の首都神月において修道士として暮らしていた。しかし、大陸を追われて来たことが神王の耳に入ると、神月からも追われることになった。このとき身重になった妻も彼に従い。また、数人の信者もこれに従ったという。
彼らは結局どこの町にも受け入れられず、珠金島の南端の村へとたどり着く。そこで、全財産を古い漁船に換えて灰銀島を目指して海に出たのだった。まるで死出の旅のように、村人の制止を振り切って海に乗り出した。村の漁師でさえ、潮の流れが強く変化の激しい灰銀島沖へ近付く者はいなかったのだ。
それから数日後、バラバラになった船の残骸が珠金島の浜に打ち上げられていた。しかし、その半分は灰銀島にも打ち上げられていたのである。
王戒と数人の従者は疲労と衰弱の極限にありながら生きてその地にたどり着くことができたのだ。そして、ようやく彼らの自由への出発点を得たのである。
新天地での彼らの生活は非常に貧しくはあったものの、神に祈りを捧げる生活には何も支障はなかった。
鬱蒼と茂る森の一部を切り開いて作られた集落も村と言えるほどに人が増え、始祖王戒もすでに他界したある年、村に3人の子供が産まれた。一人は女の子で麗(れい)と名付けられ、二人の男の子には勝(しょう)と信(しん)という名が与えられた。
その子らが10才になったある夏の日、彼らの村にヒタヒタと異変が近付いていた。
麗は村の誰よりも美しい娘に育っていた。勝は力仕事はなんでもこなすたくましさを身につけていた。そして、ロムルは天使の降臨と呼ばれる清冽さを持っていた。
その日は、いつにも増して暑さが厳しく、大人はバラックの中やテントの中でジッとしていた。3人はいつものように森の中で遊んでいた。森とは言っても、この島全体が2mを越える草木に覆われ、更に大きな大木が山をなしているため、村の外はすべて森であった。
草をかき分けて進む目的地は彼らの秘密の遊び場である「海の洞窟」だ。それは海に近い場所にあり、奥へと緩やかな勾配を下っていくと海水が溜まっていた。それはどうしてか海と繋がっているのである。彼らはその不思議な洞窟を毎日のように遊び場としていた。
だが、その日は洞窟の周りの草木が大量になぎ倒され、その入口が剥き出しになって陽光にさらされていた。そして、何かを引きずったようにいくつもの道ができていた。
「何だこれ?」
勝は長い木の棒で地面に張り付いた草を引っかきながら、その有様に驚いていた。
「ねえ、洞窟の中に何かいるのかなぁ」
麗が洞窟の入口に近寄る。
「あぶないよ」
そう言って、信もその後ろに続いた。
「俺が一番に入ってやろう」
負けん気の一番強い勝が二人を押しのけて洞窟に入って行く。彼には何のためらいもない。だが、手にはさっき拾った木の棒を握りしめている。
「じゃあ、僕も行ってみるよ」
勝が無事に入ったのを見て、信も後を追って暗闇に足を踏み入れた。
その直後、洞窟の奥にまで麗の悲鳴が反射した。
洞窟から一番に外へ飛び出したのは勝だった。続いて信も飛び出したのだが、明るい日差しが二人の視力を奪っていた。悲鳴の先で、何が起こっているのか直ぐには分からなかった。
光に目が慣れてくると大きな蛇のような生き物が映った。蛇のようだと思ったのは鉤爪の付いた短い腕と太い足があったからだ。
だが、落ち着いて観察している場合ではない。勝は棒を振り回しながらその奇妙な大蛇に撃ってかかる。その大蛇の口元に悲鳴の消えた麗の体がくわえられていた。とても、簡単には助け出せるはずがなく、勝も何度も跳ね返される。
そして、次の瞬間、ロムルはその場を離れて走り出していた。村へ戻って大人たちの助けが必要だと思ったからだ。しかし、彼はいまだにその判断が正しかったのかと自問することがある。
次々に村の大人たちが駆けつけて来て、ようやく大蛇の息の根を止めたときには、麗も勝も血の海に倒れていた。
二人は一命を取り留めたかに思われた。しかし、夕闇が訪れた頃、彼女の容態が急変し、高熱を発して見る間に体中が赤く腫れ上がったのだ。
村の誰にもその苦しみを和らげることはできなかった。おそらく大蛇の毒ではないかというで、血清を作るために夜の闇の中を大人たちは大蛇の死骸を探しに出かけた。しかし、あの大蛇の姿はどこにも見つけることはできなかった。
そうして数日、昏睡状態が続き、高熱が続いていた麗の肌はしだいに黒く毒に侵され始めた。だが、ようやく熱が収まった時には、美しい褐色の肌は右半分が赤黒いアザに変わり果てていた。
そして、麗が意識を取り戻したとき、大人たちは疲弊しきっており、子供たちは恐怖に震えていた。
彼女が熱にうなされていた数日間、村の周りを怪異な獣たちが徘徊するようになり、大人たちはそれらを追い払うことに疲れ切っていた。子供たちもまた、その異形の衆から身を隠してジッと息を潜めていなくてはならなかった。
もはや、村人の中で彼女は忌まわしい呪われた存在となっていた。人々の目は彼女自身の変貌よりも禍々しく、幼い少女にとって体の痛みより辛い心の痛みに耐えることは死より辛く感じられた。
そんな中、勝は毎日彼女のそばにいてくれたのだが、信は村人たちの信仰の象徴であり、狂信的な一部の人たちが教会の2階に彼を隔離してしまった。
それに追い打ちをかけるように、看病に疲れた麗の母親も寝込んでしまう。そして、麗の父親は非情な決断を村中から突きつけられ、もはや誰にも止められない事態が待っていた。
ついに父は村の決定に従うことを承諾した。すぐさま麗の家には大人たちにが押し寄せ、無理矢理彼女を連れ出すと、生け贄とするため海の洞窟へと運んで行くのだった。
「お前のせいだ!お前のせいで麗は村から追い出されたんだ!」
教会の2階の窓に向かって石を投げながら、勝は大声で叫ぶ。窓の内で、信はその姿を黙って眺めていた。
「こら!静かにしろ、勝!村のためにみんなで決めたことだ」
見張りの男が窓を開けて、勝を追い返そうと怒鳴りつける。
「なに?バカヤロウ!麗は何も悪くぞ!・・あっ!」
勝が上を向いて大声で言い返していたその時、窓の後方から1つの影が空へと飛び出した。それは舞い降りる天使のようであった。だが、勝はすぐにそれが信だと気がついた。あの大人しい信が彼の声に応えるように、彼の願いを聞き届ける天使のように両手を広げて落ちてくる。勝はともかく慌てて彼の体を受け止めるべく、走り回って何とかその下に潜り込んだ。
「大丈夫?勝?早く麗を助けに行こう」
直ぐに立ち上がった信は、そう言うと勝の腕を引っ張き起こした。
「助けるって、どうするんだ?」
「麗は生け贄になるんだぞ!ほら」
二人はしっかりと手をつなぐと、大人たちから逃げるために走り出した。
「何だ、そのイケニエって」
「あの悪魔のエサにされるってことだよ」
「何だ!それは許せねえ」
二人は更に村の外を守っている大人たちを振り切って一目散に洞窟を目指した。
その途中で、大人たちが慌てて逃げ帰ってくるので、二人は慌てて草むらに身を潜めた。
彼らは口々に叫びながら彼らに気付かず脇を走り抜けて行く。すると、その後を2つの首を持った虎が追いかけて行ってしまった。
「今のうちだな」
二人がそっと洞窟へ近付いて行くと、そこには見張りの姿はなく、洞窟の入口は木で作った檻がはめ込まれていた。
「麗!麗!」
二人は同時に檻に飛びついた。そして、麗も二人に応えて顔を出したのだった。
「勝!信!」
麗の涙もその変わり果てた姿も、どうしようもなく痛々しかった。二人は懸命にその柵を壊そうと、体当たりしたり、結んだ草の蔓を引っ張ったりするのだった。麗にはその姿こそ痛々しかったことだろう。
だが、それもゆっくりはしていられなかった。人間の臭いを嗅ぎつけた異形の生き物がやってきたのだ。それは馬の首にアンバランスな虎かライオンのような体をしていた。
その動きは俊敏で、二人は簡単にはじき飛ばされた。まるで、檻に張り付けになったように動けなかった。怪物は真っ直ぐに檻に向かって突撃してきた。そのお陰で歪んだ檻に子供が通り抜ける隙間ができた。
二人は洞窟の中へと逃げ込んで、麗と共にその奥へと走った。幸いあの怪物は彼らへの興味を失ったのか、追ってくることはなかったのである。
その洞窟で何日か過ごしたろうか。大人たちの呼ぶ声が聞こえたこともあったが、彼らは洞窟の奥で肩を寄せ合ってジッとしているのだった。そして、いつしか眠るように彼らは意識を失って行く。
その後、何があったかは分からないのだが、次に気付いたときには一人の異形の紳士がかたわらにいた。
その紳士こそアベル・ノイバンシュタインであった。彼を異形と感じたのは黄金の髪と青や緑に光る瞳のせいであった。
そこは狭いテントの中であった。だが、そこで食べ物を与えられ、また眠ってしまった。
そして、その後のしばらくの記憶がないようなのだ。次に記憶が鮮明に残っているのは、燃えさかる村を見ている自分たちの姿であった。その3人の周りにはあの禍々しい生き物たちも息絶えて倒れていた。
そして何よりも、3人がお互いの大きな変化に気付いたのもこのときだった。麗は毒蛇の腕を、勝は虎の頭を、信は鷲の羽と足を持っていた。だが、ことさらそれに驚きはしなかった。それを当然のごとく受け入れている自分たちがいたのだ。
村は灰となり、父も母も見つけることはできなかったろう。感傷に浸る間もなく、炎の中にアベルの姿を見つけた。アベルは3人を元気付けると、彼と一緒に大陸へ帰ることを進めた。
そうして、彼らはノイバンシュタイン伯爵の居城で暮らすことになったのである。悲しい記憶と楽しかった想い出を残して、3人は共に旅立ったのである。
時間異変
忌まわしい記憶の日から10年が過ぎ、彼らは初めて灰となった故郷の村を目にしたのだった。
誰もそのことについて言葉を発することはなかった。
食事が終了してしばらくすると、アベル伯爵が彼らの食堂へやってきた。
「どうだ、疲れは取れたかな?」
淡々と感情のない声に3人の手が止まった。
「ああ、俺は大丈夫だ」
虎男ラゴルは自分のお腹をさすりながら、後の二人に遠慮がちな視線を送る。
「やはり、疲れました」
「そうか、ご苦労だったな。ところで、王戒の遺産は見つけることができたのか?」
「いえ、あの村にはなかったようです。ゴブリンを野に放って調べさせましたが、まだ何も・・・」
ラムザは淡々と答える。そこには迷いの色は見られなかった。
「ゴブリン共は役に立たん。・・死出の旅の途中か、海の底かもしれんな・・」
「しかし、かならずや見つけて見せましょう」
「頼もしくなったな、ラムザ」
「ありがとうございます」
そこに笑顔はなかった。アベルはそれでも彼らを優しく見守っているようだった。
「まあ、今日は疲れているだろう。2・3日中に報告書を出してくれ。また、詳しい話はそれからだ」
「分かりました」
ラムザの言葉を聞いて、アベルは早々とその部屋を後にしたのだった。
老召使いアスターもその後に続いて部屋を出た。うつむきながら背後からアベルの様子を伺うように何度も目を上下に動かしていた。
アベルは黙りきったまま自室へと飛び込んだ。その眉は怒りに震えていた。
「なんたることだ。10年という時間をくれてやったというのに!」
その怒声は部屋中を揺らした。書斎机の上にあった本や書類を投げ散らかして、そのままうつ伏せになってしまった。
アスターはドアの外からノックをして声を掛けた。
「アベル様、失礼いたします」
ドアを開いて、アスターは驚くほどズカズカと中へと踏み込んできた。そして、優しくアベルの背中をさすっている。
「アベル様、まだ時間はあります。あなたには時間を支配するお力があるではありませんか。彼らとて無能の輩ではございませぬ」
それは幼い子供をあやすような口調のようであった。
「分かっている。しかし、私には1年という時間だったが、あやつらの監視役としておまえもミレも10年という時間を過ごしてしまった」
アベルは悔しそうな鳴き声混じりの声で、素直に口を開いた。
彼らノイバンシュタイン城の者たちはこのオリエンタル・ドミニアを含む世界の住人ではなかった。彼らは別次元のドミニアからの来訪者なのだ。
その上、二つの世界は時間の流れが10倍も異なっている。そのため、元の世界で暮らすアベルは1年を過ごし、同時にこちらの世界にいるアスターは10年を過ごしたのであった。
彼らの世界は長く戦乱の絶えない大陸に数多くの国家が存在していた。その中でも最も広大な領土を持っていた彼らのアルハイム帝国は数々の悲劇の中で次第に国力に翳りを見せ始めていた。
彼らの憂いの最大の原因はそこにあり、そして、そこに居場所がないことでもあった。
アスターも忘れかけた故国の風景を思い返していた。
「それは良いのです。私もミレもアベル様にお仕えすることで本望です。例えお側におれなくとも私たちはアベル様のお役に立っておればそれで十分でございます」
アベルは唇を噛み締めながら顔を上げた。
「この1年で、我が帝国はさらに苦況に立っている。場合によっては明日にもクーデターが起こって滅び行く可能性もあるのだ。私はアルハイムの地を離れたくはない」
「分かっております。私もアルハイムの民、お父上ライン様のお若い頃より帝国に使えておりました。国を思う気持ちはこの10年で薄れるものではありません」
老翁アスターの目は、若くして戦場を駆けめぐった頃の輝きを失ってはいないようだった。
アベルはアスターの目を見て気力を奮い立たせる。背筋が真っ直ぐに戻った。
「そろそろアルハイムに戻らねばならん。報告書は預かっておいてくれ。8時間後にはまたこちらに来られると思う」
「分かりました。3日後になりますな。あまり無理をなされませんように。最近、次元移動の回数が多くなっておりますので・・」
「うむ、王戒の遺産さえ見つかれば疲れなど吹き飛ぶのだ」
「それは、おっしゃいますな。彼らとてアベル様のためにと思っております」
「分かっている・・」
アベルは衣装を地味な物に着替え始めた。
「エルバ=ヴァン公爵が軍の実権を握った。あの男を止められるのはアスター、おまえだけだった」
「・・あやつなら老いた母がいる限り何もできませぬ」
「その母君が亡くなられたら・・?」
それはもはや仮定ではなく、その結果が現れてきているのだ。
「・・・そう・・ですか。打つ手はありませぬなぁ・・」
「考えておいてくれ、あと2・3日は保たせておくが、諸侯の心変わりが早く影響を及ぼしそうだ」
「ともかく、ランベルト殿が生きておられたなら・・・」
「伝説の男か・・。今は、目立つことはできぬ。ラムザたちを連れて帰りたいのだがな」
ため息ばかり吐くアベルの姿は痛々しく、アスターも自身が行動できないことを歯がゆくて仕方ない様子だ。
「ともかく、ランベルト殿の手がかりを集めておいてくだされ」
「ああ、だが最近妙なことを考えるようになった」
「妙なことですと?」
「そうだ。王戒こそ失踪したジョアン・ランベルトではないかということだ」
これにはアスターも言葉を失った。それは、彼らが遺産探しに利用しているラムザ達がその子孫ということを意味する。
「まあ、それはともかく、王戒の遺産こそ探し求める力であることは間違いない」
アベルは奥の部屋へと続く扉を引いて開けた。
「留守を頼んだぞ」
そう言うと、真っ暗な部屋の中へと消えていった。そして、アベルは次元を越えて元の世界へと戻っていくのだった。
残されたアスターはしばらくその扉の向こうにある懐かしい世界へ思いを馳せ、目を閉じたまま立ちつくすのだった。
その頃、ラムザ達3人はヒソヒソと何やら話を始めていた。あのラゴルですら難しい顔をして考えを巡らせているようだ。
「今なら、伯爵はしばらく戻っては来ないだろう」
「アスターとミレも今頃安心しているはずよ」
ロムルとラムザの言葉でラゴルも状況を理解したらしく、大きくうなずいた。
「でも、本当に大丈夫なのか?」
「何をいまさら・・」
変に臆病なことを言うラゴルにラムザが叱咤する。
「勝(しょう)、あなたはこのままで良いと思っているの?私は嫌よ。忌まわしい体と忌まわしい名前をもらって生き続けるなんて・・・」
「そ、それは・・。分かってるよ」
常にラムザの身を案じるラゴルには彼女の気持ちは痛いほど分かっていた。しかし、このノイバンシュタイン城の外に自分たちが安穏と暮らす場所がないことも分かっているからだ。
「いつまでもこんな所にいる訳にはいかないよ。今でこそ、暖かい毛布の中で眠れるようになったとは言え、辛いことが多すぎた・・・」
ロムルの言葉に10年間の苦悩が染み込んでいた。
ラムザの目に涙が浮かぶ。ラゴルはあわててテーブルのナプキンを取り、彼女の涙がこぼれないようにするのだった。
「・・・ありがとう、勝」
「ああ、分かったよ。麗(れい)、お前は今でもあのころのままだ」
「そうだよ。3人でやり直そう。村へ帰ろう。伯爵もきっと分かってくれる」
ロムルも静かに2人を励ます。
「そうね。あの村なら気兼ねなくやり直せるかも知れない」
彼らの夢も希望も膨らむばかりだった。
その時、部屋の扉がおもむろに開いた。そして、怒りの形相のミレが入ってきた。
「あなたたち、妙なことを考えているのね」
ラムザを守るように2人の男がその行く手を遮る。
「私はあなたたちのおかげで、この城内で10年という長い時間を過ごしてきたのよ。父もそう。伯爵もあなた達をここまで育ててくださったのに・・・。それを裏切るというの?」
「私たちは道具ではないわ。もう、自分たちで生きて行きたいのよ」
「外の世界にあなたたちを受け入れてくれる場所があるというの?人を果実のようにもてあそぶあなたたちに、平穏な安息が約束されていると思って?」
ミレはいつも以上の早口でまくし立てる。これには押し黙ってしまう3人だが、ラゴルの目は怒りにはじけそうだ。
「ミレ、あんたもその果実と同じだと分かっているのかい」
ラゴルの野生の迫力にもミレは怖じける様子は見せない。それは彼らを幼少から知っているからだ。
「ふん!私はもう朽ち果てるだけ・・・。それに、あなた達が出て行くならそれでスッキリするもの」
「それなら、黙って行かせてください。そうすれば、あなたに危害を加えたりはしないでしょう」
ロムルが落ち着いた優しい声で、彼女の気を沈めさせる。
それに対して、ミレは一歩踏み込んだ。
「でもね、伯爵がお留守の間に城を出るなんて、私は許さないわよ」
「あんたの許可はいらないんだよ」
「所詮、選択の余地はないのよ。それならこのまま消えてしまいたいの。もちろん、王戒の遺産は探してみせるわ。でも、それは私たち一族の最後の思いかもしれない。それを売り渡す以上、ここで安穏とはしてられないのよ」
ラムザも前の2人を押しのけるように体を乗り出して、ミレをにらみ付けた。
「それは見つけてから言うことね」
「・・・見つけたのよ」
その言葉に偽りはなかった。ラゴルもロムルもしまったという顔でラムザを振り返ったからだ。
「ほ、本当なの?」
それが本当なら彼女も元の世界へと戻ることができるという希望となる。ましてや、この手の掛かる3人がいなくなるならなおさら、それは現実のこととなるだろう。
「それはどこに?戻ったときは何もなかったわね」
「ちゃんとあるさ」
「ここへ戻ってくる途中で隠してきたよ」
ラゴルが下手に言ってしまわないように、ロムルがその言葉を引き継いだ。
「簡単に人間が入れないところにね・・・」
「じゃあ、王戒の遺産というのはやはり聖なる石だったの?」
「そうね。血のように赤く美しい石だったわ」
ラムザの瞳の奥に赤い炎が見えた。それは幾重もの屍を作り出した狂気の光に見えた。ミレは初めて恐怖に退いた。そして、これが彼女の最後の言葉となった。
身を翻したラムザとそれを追った2人は塔の最上部へと階段を駆け上がり、ロムルの足に捕まって暗闇に飛び立った。
月明かりに照らされた彼らの影をミレは窓から凝視していた。
闇の絨毯が広がる森の中へと彼らは消えていった。遠くで野犬の遠吠えが聞こえているようだった。
「どこへ行こうと、あなた達はここへ戻ってくる。・・・ここがあなたたちの生まれた場所だから・・・」
そうつぶやいたミレの横顔は何故か寂しげであった。
明るい月の輝きの中で、すべては見透かされたように透明だったに違いない。しかし、その向こうに広がるのは漆黒の闇であった。どちらが、彼らの目の前にあったのか、それはまだ分からない。



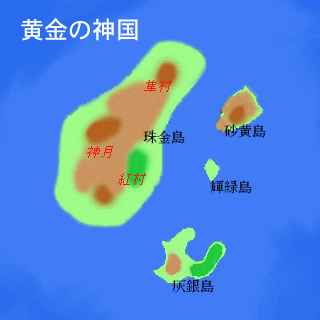 黄金の神国は珠金島と3つの島を領土としている。砂黄島には砂丘があり、輝緑島には深い森がある。そして、南にある灰銀島には人を寄せ付けぬ海流があった。
黄金の神国は珠金島と3つの島を領土としている。砂黄島には砂丘があり、輝緑島には深い森がある。そして、南にある灰銀島には人を寄せ付けぬ海流があった。